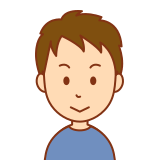
家計簿ってなんでつけるの?
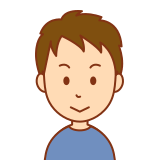
家計簿を付けたら何をすればいい?
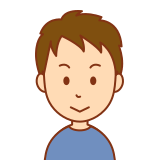
家計簿をつけたいけど何から始めれば良いのかわからない
そんな疑問を抱える方へ向けて、『家計簿の果たす役割』と『家計簿の付け方』をできるだけわかりやすく解説します。
家計簿をつけたことがない人、三日坊主で終わった経験がある人でも、本記事を参考にして家計簿を付けてみましょう。一から順を追って解説しているのでご覧ください。
目次
家計簿の役割
まず初めに家計簿とは、家計における収入と支出をまとめた帳簿(ノート)のようなものです。
一ヶ月単位で区切り比較することで、無駄な出費や節約できる費用を把握することができます。
お金の収支を把握し使い方を見直すことで、貯金額が増えたり、趣味・娯楽にお金を使えるようになり今より豊かな生活を送れるようになるでしょう。
ですが、家計簿をつける際は以下のことに気をつけましょう。それは、
『家計簿をつけることが目的化してしまう』ことです。
家計簿をつけること自体は目的ではありません。家計簿をつける本当の目的は『家計の現状を把握して見直す』ためです。現在どのようなお金の使い方をしており、どのようにすれば改善できるか分析し見直さなければ意味がありません。
家計簿をつけることはあくまで手段であり目的ではありません。この意識があるだけで、無駄な努力をしてしまうことを防げるでしょう。
家計簿の種類と特徴
家計簿にはいくつかの種類があります。家計簿をつけ始める前にそれぞれの特徴を知り、自分にとって使いやすい家計簿を選ぶことが重要です。もちろん家計簿を付け始めて「自分に合わない」と思ったら他の方法を試してみるのも良いでしょう。
手書きの家計簿
ノートに費用項目を自分で書いたり、市販の家計簿帳を使って記録していく方法です。
ノート型の家計簿であれば自分好みにカスタマイズしたり、デコレーションができ自由度が高いのが魅力的です。市販の家計簿であれば、費用項目がすでに印字されておりすぐに使い始めることができるので初めての人にもおすすめです。
手書きの家計簿のメリットとして、手書きすることで自然と脳内で記憶し金額を把握したり、ページの余白などに目標や改善点などメモできることが特徴です。
デメリットとしては、記入や集計を全て自分で行うため手間がかかることです。また、家計簿帳そのものがないと記録できないため、出先での出費や見えない支出(引き落としなど)が合った場合記入漏れが発生する可能性があります。。
Excelなどの表計算ソフトの家計簿
表計算ソフトに費用項目を入力し、レシートなどを参考に記録していく方法です。
表計算ソフトの家計簿であれば、手書きするよりも手間が減り、集計する際にも関数やグラフを用いることでより詳しく分析することができます。ネットで公開されているテンプレートを利用することで、一から費用項目を入力する作業もなくなります。
身近にパソコンがあり、パソコン作業が得意な人であればオススメです。
デメリットとしては手書きの家計簿と同じく、パソコンそのものがないと記入できない点で記入漏れが発生する可能性もあります。
家計簿アプリ
スマホでアプリをインストールして、家計簿を付けていく方法です。
家計簿アプリであれば、支払いの直後にスマホで入力でき、記入漏れを防ぐことができます。また、アプリによって機能は異なりますが、レシートを読み取って自動入力できる他、口座やクレカを登録することで引き落としなどの支出に対しても漏れなく記入することができます。集計作業やグラフかも自動でしてくれる為スマホを普段から使用している人には一番オススメです。
完全無料で利用できるもの・課金することで幅広い機能を利用できるものなど色々あります。
デメリットとしては、普段からスマホの扱いに慣れていない人や、セキュリティー面で情報漏洩・お金をアプリで管理されるのに抵抗がある人は導入しづらいかもしれません。アプリを選ぶ際は安心できる提供先を選ぶことも重要です。
以上で紹介した家計簿の種類の中から自分に最もつけやすそうなもの、継続できそうなものを選べたら次は、家計簿をつける手順を身につけましょう。
家計簿をつける基本的な流れ
家計簿の主な費用を打ち出す
テンプレートを使用される方、スマホアプリで家計簿をつける方は、すでに項目が準備されているので飛ばして構いません。
家計にとっての費用項目は多岐にわたります。費用を多く作り過ぎてしまうと統一感がなくなり、把握が難しくなってしまうため、はじめはシンプルにまとめるのがコツです
固定費とは、毎月金額がほぼ変動しない費用のことで、以下のものが挙げられます
| 住居費 | 月々の家賃、住宅ローンなど |
| 水道光熱費 | 電気代、ガス代、水道代 |
| 保険料 | 生命保険、自動車保険など |
| 通信費 | スマホの利用料金、Wi-Fiなどの固定回線費 |
| サブスク費 | Amazonプライム、Netflix、ジムなど |
変動費とは、月ごとに金額が変動する費用のことで、以下のものが挙げられます
| 食費 | 食料品、外食代、飲料代など |
| 日用品費 | 消耗品(トイレットペーパー、洗剤など) |
| 交通費 | バス、電車、車など |
| 衣服費 | 衣服代 |
| 医療費 | 診察代、薬代、検査代など |
そのほかたくさんの費用項目がありますが、まずはこの程度の種類から始めてみると良いでしょう。続けていくうちに項目が増えていくのは当然のことですが先ほど述べたように増やし過ぎには注意です。
予算と締め日を設定する
何にどれくらいお金を使うのかを決めましょう。予算の立て方は人それぞれですが、迷ったら50/30/20ルールを活用してみましょう。これは、手取り収入の50%を固定費や生活費に、30%を娯楽に、20%を貯蓄に回すという考え方です。特にこだわりがないようであれば50/30/20ルールを活用してみても良いかもしれません。
予算を決めたら、毎月の締め日を決めましょう。家計簿における締め日は基本的に『月末』がオススメです。月末締めにするとスタートする日が一日スタートとなり、月によって変動がないため管理しやすいと言えます。
他には『給料日前日を締め日』とし、給料日をスタート日とする方法もあります。給料日スタートだと支給日が銀行の振り込みの都合上必ずしも決まった日に振り込まれないことがあるため、混乱してしまう可能性があります。
記入日の設定とレシートの保管
家計簿の準備、予算と締め日を決めたらいよいよ家計簿に記入していきます。
理想は毎日記入することですが、忙しい方や収支の動きが少ない人は一週間分まとめてつけてもOKです。家計簿はとにかく継続することが重要なので、自分の負担にならないように工夫しましょう。
スマホアプリを利用し家計簿を付けいていく人は、支払いをした直後にアプリを開いて記入することで記入漏れがなく継続できるので忘れないうちにつけておきましょう。
また、レシートの保管をすることで自分が入力した内容に漏れがないかチェックできるのでファイルや封筒などに入れておきましょう。
さらに、クレカ支払いや口座引き落としなどがある場合は、クレカを使用した時にすぐにメモを取ったり、引き落としの場合は、設定した記入日に一緒に確認すことで記入漏れを防ぐことができるでしょう。
締め日で振り返りをする
全てはこの時のために家計簿を付けきました!
締め日または、その翌日のタイミングで一ヶ月分の結果を振り返り、分析を行います。予算オーバーの場合は翌月以降繰り返さないための対策を考えましょう。
食費の使い過ぎの場合は、外食を減らす、自炊を増やす。衣服を買い過ぎたら翌月はできる限り抑えるなどの方法で上手に付き合っていきましょう。
これを毎月繰り返して無理のない程度に継続することでだんだんと効果が出始め、気付かないうちにお金の使い方が上達して貯蓄が増え、余裕のある暮らしが実現できるでしょう。
最後に大切なことを一つだけ紹介します。
家計簿の残高合わせはしなくて良い
家計簿において最後の関門が残高と帳簿上の金額を合わせる作業がありますが、これはしなくても良いと私は思います。
再度集計し直すことは大切ですが、効率がとても悪いです。残高を必死に合わせるよりも固定費の見直しによって継続的な節約をすることのほうがよっぽど効率が良いと考えます。
残高を合わせるのは何度も行っているとストレスとなり、家計簿を辞めてしまう理由にもなります。
あまりにも大雑把な家計簿は意味がありませんが、ある程度丁寧につけているのであれば自分を信用して、気にせず処理してしまいましょう。
まずは行動してみよう
本記事で紹介した内容を全て実践してください。と言われても面倒だと思います。
まずは、家計簿をつける目的をはっきりさせ、自分を納得させることから始めてみましょう。
家計簿をつけるにあたって必要なものはスマホさえあれば誰でもできます。
ハードルを高く設定し過ぎずに自分のやれる程度から始めて、継続することを大切にまず何事も行動してみることで、あなたの人生がより豊かなものになるでしょう。


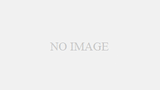
コメント